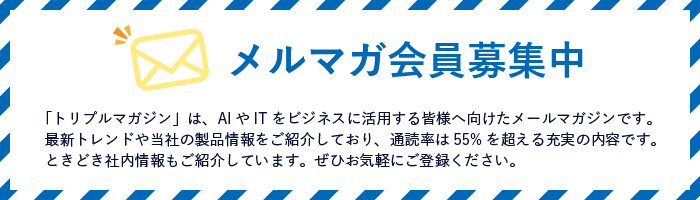IR活動での「失敗しかけた」エピソードを赤裸々に語る〜CFO加藤が「しくじりそうだった先生」に登壇
- 2024.12.12
こんにちは。
トリプルアイズ広報の白石です。
トリプルマガジンでは、当社の製品やサービスについてはもちろん、IT・AIに関する最新情報を発信しています。たまに社内の出来事もお知らせします。⾝近に感じていただけると嬉しいです。
今回のコラムでは、IR活動での「失敗しかけた」エピソードを赤裸々に語る〜CFO加藤が「しくじりそうだった先生」に登壇という内容でお届けします。
ニュースでは
▪️ トリプルアイズ本社移転のお知らせ
▪️ 取締役・加藤慶が「しくじりそうだった先生」に登壇
▪️ ASCII.jpで紹介「アルろく for LINE WORKS」
をご紹介します。
「今日から使えるChatGPTビジネス活用Tips」ではChatGPTにまつわる小ネタをご紹介します。
最後に、IT批評では
12月のSTORY メガ自治体・世田谷区が取り組む「脱・紙管理」
12月の編集長レビュー マスメディアは何に負けたのか?インテリジェンス・トラップとメリトクラシーの地獄
12月の特集記事 半導体エネルギー研究所顧問・菊地正典氏に聞く
をご紹介します。
ぜひ最後までお付き合いください。
【目次】
1.IR活動での「失敗しかけた」エピソードを赤裸々に語る〜CFO加藤が「しくじりそうだった先生」に登壇
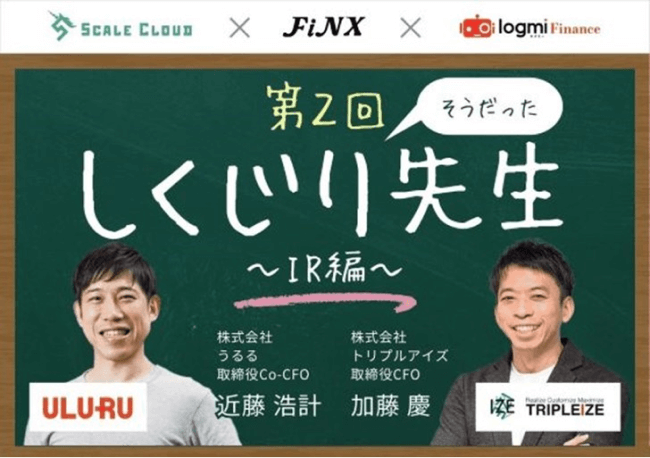
12月4日(水)に開催された「第2回 しくじりそうだった先生 ~IR編~」に、当社取締役CFO・加藤慶が登壇しました。
本セミナーは、上場後のIR活動において直面する課題や、対応の難しさについて経験や知見を共有し、さらに投資家やステークホルダーとのコミュニケーションを通じたリスク軽減と成功への道筋を探ることを目的に開催されました。当日は経営層やIR担当者を中心に多くの方にご参加いただきました。
セミナーでは、株式会社うるる取締役・近藤氏と当社・加藤の2人が登壇し、 IR活動における課題や「失敗しかけた」エピソードを紹介。資本政策の判断や投資家対応の難しさについて実体験を交えながら、ここでしか語れない内容を赤裸々にお伝えしました。参加者の反響が特に大きかったのは説明会対応時の注意点についてのTipsで、参考になったというお声を多くお寄せいただきました。さらにIR活動で重要視している点として、投資家一人ひとりを「トリプルアイズを応援するファン」と捉える姿勢を持っていると加藤より語られました。具体的な対応として、誠実かつポジティブな情報の伝え方を心掛け、独自性を打ち出すことが、投資家との信頼関係を構築する鍵であると強調しました。
最後に、「投資家にどのように受け取ってもらいたいかを常に意識したIR活動が、信頼の礎を築く」というメッセージでセミナーは締めくくられました。
ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました!今回の内容が皆様のIR活動のお役に立てば幸いです。
今後もトリプルアイズの情報発信にご期待ください。
2.トリプルニュース
■トリプルアイズ本社移転のお知らせ
2024年11月25日(月)より本社を移転しました。
新住所は下記の通りです。
所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦3ー4ー1 グランパークタワー32F
https://www.3-ize.jp/information/5081/
■ 成長企業のCFOが語るIRの経験談 取締役・加藤慶が「しくじりそうだった先生」に登壇
https://www.3-ize.jp/information/5164/
■ASCII.jpで紹介
アルコールチェックが安価で簡単な「アルろく for LINE WORKS」
https://www.3-ize.jp/information/5195/
3.今日から使えるChatGPTビジネス活用Tips

このコーナーでは、業務ですぐに利用できるChatGPTの簡単なコンテンツをお届けしていきます。業務効率化や会話の小ネタとしてお役立ていただけると幸いです。
ChatGPTが登場してから2年が経ちました。2024年5月時点で月間訪問者数が23億人を超え、ビジネスはもちろん、私たちの生活にも深く浸透していることがわかります。
今回は生成AIの次に訪れる「AIエージェント」の時代についておもしろい記事を見つけたので、ご紹介します。
時代は生成AIからAIエージェントへ
https://www.mri.co.jp/knowledge/opinion/2024/202412_1.html (三菱総合研究所)
生成AIの次なる技術革新として注目されているのが「AIエージェント」です。
AIエージェントは、人間の指示を自律的に分解し、柔軟に対応する技術だと言われています。単なるタスクの遂行にとどまらず、複雑な問題解決が可能なことより、ビジネスや日常生活での利用が加速すると期待されています。
AI技術の進化の流れ
AI技術は「予測AI」から始まり、現在の「生成AI」を経て、次の「AIエージェント」へ、さらには「汎用AI」や「超知能」に至ると考えられています。この中でも「AIエージェント」は、産業分野において特に注目されており、企業活動や社会全体に大きな変化をもたらす可能性を秘めています。
AIエージェントの活用事例として、次のようなものが挙げられます。
BtoB分野
顧客対応の自動化(カスタマーサポート)
ソフトウェア開発支援
専門知識を活用した研究支援
BtoC分野
ショッピング支援
健康管理プランの提供
ゲーム体験のパーソナライズ化
さらにAI同士が協力し合う「マルチAIエージェント」の応用も見込まれています。
自律性の高いAIエージェントには大きな利便性がある一方、リスクも伴うことが懸念されます。
例えば、機密情報の漏洩、誤った動作やAIの暴走などが考えられます。これらに対応するため、セキュリティ技術やAIの行動を監督する仕組みを整備の必要性がより高まってくることでしょう。
AIエージェント時代の到来に備え、企業が取り組むべきことは3点あると考察されています。
■業務環境のデジタル化
文書や業務プロセスの標準化、API整備など、AIが活用できる基盤を構築する。
■人材育成
AIツールのスキル向上や問題解決力の強化を図る教育を進める。
■新サービスの開発
アジャイル型組織の導入や外部連携を活用し、迅速なサービス開発を進める。
生成AIが登場して、インパクトを感じている方も多いと思います。私もそのひとりです。今後のAIエージェントの普及は、業務効率化にとどまらず社会全体の価値観やシステムの変革をもたらすことになり、より大きなインパクトを私たちの働き方や生活に与えることになりそうですね。
明日9:00公開の「おっさんのおっさんによるおっさんのための生成AI」動画は
営業マン必聴!胃が痛くなるような毎日がテクノロジー活用で救われる? という内容でお届けします。
経営者はAIで効率化を求めるけれど、現場の社員が求めるものはこっち!? ぜひご覧ください!
https://www.youtube.com/channel/UC9hwNvLD4jGP8FUQOSsqtbw
ゼロから始める「ChatGPT業務効率化実践講座」
https://www.3-ize.jp/chatgptkouza/
講座の詳細はお問い合わせください。
4. IT批評
12月のSTORY メガ自治体・世田谷区が取り組む「脱・紙管理」

2024年8月、世田谷区では、会計年度任用職員(従来の非常勤職員やアルバイト職員に相当)に顔認証による出退勤管理システム「AIZE(株式会社トリプルアイズ)」を採用し運用を開始しました。
運用開始より3カ月を経て、自治体におけるDXの現状と課題について、世田谷区人事課係長・鈴木さん、人事係・中村さん、人事係・白石さんにお話をお聞きしました。
第1回 顔認証が勤怠打刻システムに採用されたわけ
第2回 いかにしてデジタル・デバイドを乗り越えていくか
https://it-hihyou.com/category/all/story/
12月の編集長レビュー
マスメディアは何に負けたのか?インテリジェンス・トラップとメリトクラシーの地獄
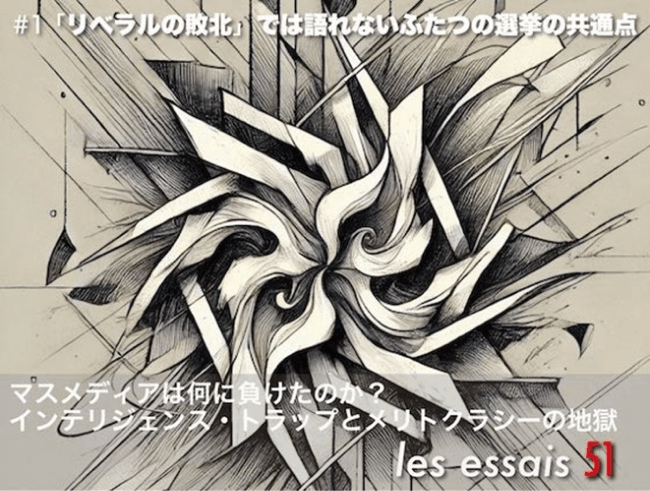
11月に行われたアメリカ大統領選挙と兵庫県知事選挙はどちらも返り咲き当選でした。これらの結果は何を意味するのでしょうか。能力主義がもたらす政治的な対立構造について語ります。
第1回 「リベラルの敗北」では語れないふたつの選挙の共通点
第2回 能力主義の罠 サンデルが問う社会の歪み
第3回 自分都合に事実を解釈する賢い愚か者
第4回 能力測定社会がわたしたちを壊す
第5回 知恵あるAIが導く「人間らしい社会」の再構築
https://it-hihyou.com/category/all/review/
12月の特集記事 半導体エネルギー研究所顧問・菊地正典氏に聞く

国も企業も電子立国復活を目論み、半導体事業に対して何兆円クラスの投資が行われています。半導体黎明期から技術者としてかかわってきた菊地氏に半導体業界の現在と将来について伺いました。
第1回 理論を実践に 先駆者が語る半導体開発の軌跡
第2回 半導体の「ばらつき」に秘められた技術革新の可能性
第3回 TSMCに学ぶビジネスモデル革新の必要性
第4回 日本の先端半導体挑戦に必要な条件とは
第5回 日本が無視できない技術大国になるために
https://it-hihyou.com/category/all/feature/
5. 編集後記
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
師走に入り、年の瀬の雰囲気が深まってきましたね。こんなタイミングでのご挨拶となり恐縮ですが、月末より産休に入らせていただくこととなりました。皆様、いつもトリプルマガジンをお読みいただきありがとうございます。メールをお送りした後にデータを振り返ると「通読率」が高く、皆様の大切なお時間にお読みいただけていることに感謝の気持ちでいっぱいになります。
次号より新編集長が着任いたしますので、ぜひお楽しみに。少し早いですが、来年もトリプルマガジンをよろしくお願いいたします。
それでは、次号もお楽しみに!